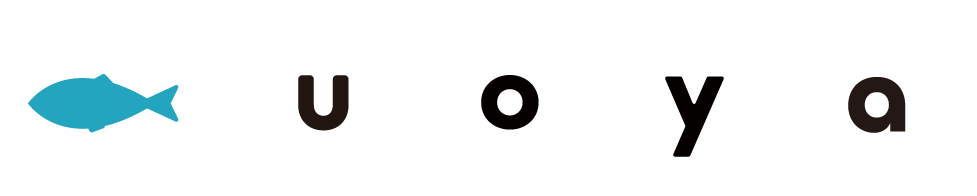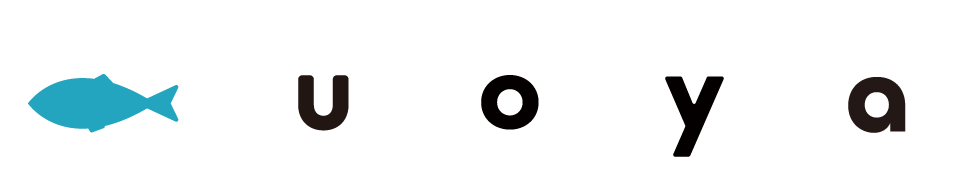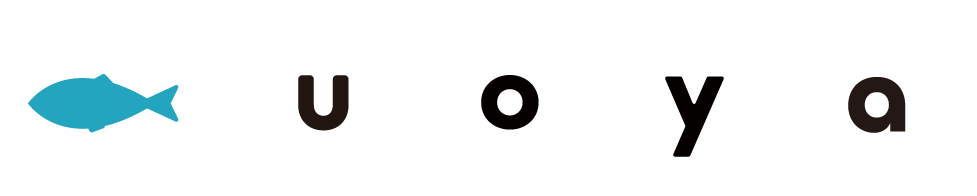旬の魚は、まるで季節から届く手紙のようだ。その時期ならではの魚介が食卓に上ると、私たちは自然と季節の移ろいを感じ取る。東北から関東沿岸でも、海には四季折々の主役が現れ、港や食卓を彩ってきた。
春を告げる魚たち
春、北国の漁港には色とりどりの大漁旗がはためき、海にも季節の訪れが感じられます。魚の世界にも「春の使者」がいます。その名も「春告魚(はるつげうお)」。かつてはニシンが春告魚の代表格でしたが、現代では春先に各地でよく獲れる魚を指す言葉です。
例えば関東では、2月1日の東京湾メバル釣り解禁日が待ち遠しい存在。大きな瞳のメバルは春告魚として釣り人に親しまれ、脂の乗った身は煮付けや刺身で上品な甘みが楽しめます。一方東北では、雪解けの川を遡るサクラマスが桜色の婚姻色をまとい、春の風物詩となっています。魚たちが告げる春の便りは、寒さの中にも季節の変化が訪れたことを教えてくれます。
夏の海からの贈り物
初夏、黒潮に乗って初ガツオが房総沖に現れる頃、江戸の人々は競ってこの初物を味わいました。その人気ぶりは、「初鰹は女房を質に入れてでも食え」という言葉からもうかがえます。脂の少ない初ガツオは、刺身や藁焼きのタタキでさっぱりと食され、夏の訪れを告げる江戸の風物詩でした。
やがて梅雨が明ける頃、北の海は豊穣の季節。岩手県久慈の海では海女たちが冷たい海に潜り、ウニやアワビを素潜りで採る伝統が今も続きます。良質な海藻が茂る三陸の磯はウニの宝庫で、夏に旬を迎えるウニは殻ごと塩水に浸して味わえば磯の香りが際立ちます。また、宮城名物のホヤは5月〜8月が旬で、梅雨明け頃に旨味が増す磯の風味豊かな珍味です。独特の香りと甘みがあり、酢の物や刺身で地元に愛されています。夏の海の幸は、強い日差しに負けない生命力を私たちに届けてくれます。
秋の実りと冬の恵み
秋の声を聞く頃、北の海には銀色の秋刀魚が群れ、港は香ばしい塩焼きの煙に包まれます。北海道から三陸沖で水揚げされるサンマはまさに秋の味覚。脂の乗った新鮮なサンマは刺身でも格別で、旬の時期にしか味わえないご馳走です。川では鮭が遡上し、秋鮭はちゃんちゃん焼きなどの郷土料理で食卓を賑わせます。
やがて冬が来ると、海の恵みはさらに滋味を増します。冬の海の王者ともいえる存在がアンコウです。茨城県大洗沖のアンコウは「西のふぐ、東のあんこう」と称されるほど全国的にも評価が高く、11月〜3月に肝が肥大する寒い時期が最も美味とされています。ヌルヌル滑るアンコウはまな板で捌きにくいため、漁港では頭を吊るして解体する吊るし切りにします。骨と顎以外の全ての部位を余すところなく鍋に入れ、アン肝のコクが溶け出した味噌仕立てのあんこう鍋は、寒い冬に身体に染み渡る絶品です。冬の漁村では、湯気の立つ鍋や脂が乗ったブリの照り焼きが何よりのご馳走。四季折々の海の幸があるからこそ、冬を越す楽しみもひとしおです。
こうして魚たちは季節の手紙となり、私たちに四季の喜びを運んできてくれるのです。