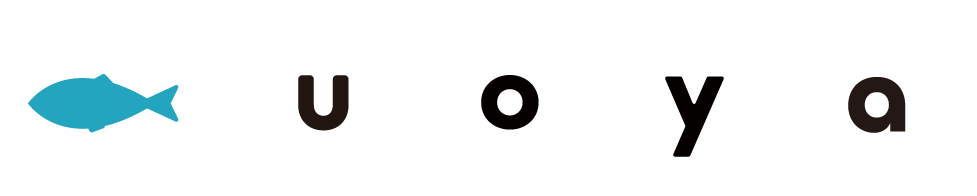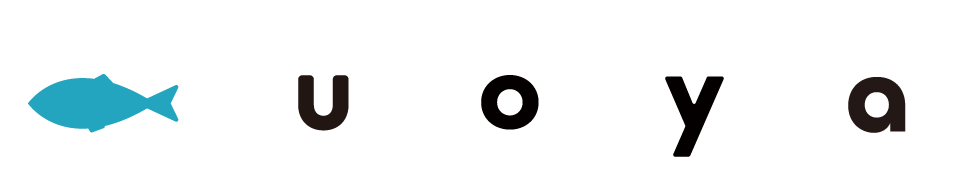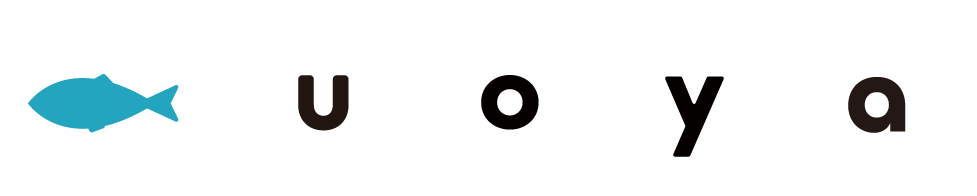骨まで味わう日本の知恵と旨み
魚を料理するとき、頭や中骨などの「アラ」はつい捨ててしまいがち。しかし日本の食文化では、この魚の骨やアラにこそ隠れた旨みがあると古くから知られています。例えば、煮干し(煮干しいわし)は小さなイワシを丸ごと乾燥させた出汁(だし)素材で、骨ごと煮出すことで濃厚な旨みがスープに溶け出します。煮干しには旨み成分が豊富に含まれ、その味の主役となっています。小魚を骨まで丸ごと食べればカルシウムなど栄養も余すところなく摂取できるため、昔から「もったいない」精神で工夫されてきた知恵なのです。
東北に息づく“アラ汁”文化
特に、東北地方では、魚の頭や骨まで活用する郷土料理が各地に伝わっています。三陸沿岸で冬によく食べられるメヌケ(深海魚)の「あら汁」は、家庭の定番料理の一つです。また宮城県気仙沼市では、新鮮なカツオをさばいた際に出る頭や中骨を味噌汁に入れる「カツオのあら汁」が有名で、魚をあますことなく食べる当地域の食文化を象徴する一品となっています。
アラから染み出すコク深い出汁は、身の部分に負けない旨みを持ち、寒い土地の食卓を温かく彩ってきました。捨ててしまえばただの骨も、鍋に入れればごちそうに早変わり――先人たちは日常の中でそのことを知っていたのかもせれません。
骨せんべいとモッタイナイ精神
魚の骨の美味しさは汁物だけではありません。刺身や煮魚の後に残った骨は、家庭ではよく油で二度揚げして「骨せんべい」にします。お米や粉を使わずとも、カリッと揚げればまるで煎餅のようなおやつになり、そのままでは食べられず捨てられがちな骨が香ばしい珍味に生まれ変わります。こうした骨までおいしく味わう工夫もまた、魚食文化の“もったいない”精神そのものです。
「魚のアラは、そのまま捨ててしまえばごみになってしまう。でも使えば立派な食材になる」
――魚の骨に詰まった旨みを引き出す知恵は、フードロスを減らすエコな取り組みとしても改めて注目されています。おいしく食べ切る工夫で命を無駄にしない日本の食卓。その背景には、魚の骨一本に至るまで味わい尽くそうとする文化的なまなざしが息づいています。魚の骨には本当に旨みがある──先人の知恵とともに、その事実が現代の私たちにも優しく語りかけてくれるようです。